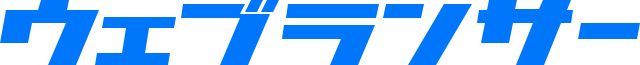『天気の子』は何を描いたのか。新海誠監督の決断が予想以上に凄かった理由(作品解説・レビュー)

2019年7月19日、新海誠監督の映画『天気の子』が公開された。この作品は、前作の『君の名は。』が驚異的なヒットを飛ばしたことで、監督の作品史上、最も注目を集めて封切られることとなった。
期待を高めすぎたり、深読みしすぎた結果、映画を観る前と観た後で全然違う印象を持った人も多いのではないだろうか。監督本人が語っている通り「賛否両論」ありそうな内容である。
単刀直入に言って、この映画はどうだったのか。
結論から言えば、個人的な総評は「凄かった」の一言である。これが「面白かった」や「感動した」でない点については後に書く。作品を観終わった直後に気づいたのは「セカイ系への回答」が成されているという点だ。そして、改めて考えた時に浮かんだのは「リセット」という言葉だった。
これから『天気の子』を鑑賞しようと思っている人は、ネタバレを避けるために、ここで読むのを止めてしまって構わない。とにかく、余計な知識や事前情報を「リセット」して、作品そのものと向き合った方が良い。そして、「セカイ系」などという言葉で一括りにするようなレビューや感想も、一切「リセット」することをおすすめする。
そんな時代は終わったんだ、時代は令和に変わったんだ、僕たちはこのような時代に生きてるんだ――と実感するような「凄み」が、この映画にはある。新海誠は『君の名は。』を超える次元の作品を生んだ。これが率直な感想だ。
※以降はネタバレを含みます。本編を観終わった人に向けた内容です。
『天気の子』は「誰」に向けて作られた作品か
『天気の子』は広く一般大衆を意識して作られた映画だ。そして、この物語の主なターゲット層は若者である。それは監督本人がインタビューで語っている。したがって本作品は、中学生から高校生くらいの若い年代にこそ観てもらいたい映画となっている。
当然、色んな年代のあらゆる人たちが観るのは自由だ。ただし、上記の前提を了解した上で観た方が、高い満足感が得られるのではないかと思う。アニメを長年観てきた人や、日常的に消費するコアなファンにこそ、若者の視点を借りて純粋な気持ちで観て欲しい。アニメに対する「知識」を一回「リセット」した方が、新鮮な驚きを得られるはずだ。
劇場用としてはどうだろう。友人同士で行っても楽しめるし、恋人同士のデートにも向いている。一人で観に行ってもいいし、二回以上の鑑賞にも耐えうる。その意味で『君の名は。』と同じくらいの、普段アニメを観ない人にも娯楽として取り入れて欲しい作品であった。
物語それ自体は、今までの新海作品を観たことがない人でも問題なく楽しめる内容だった。もちろん『君の名は。』で初めて新海監督の世界観に触れた人でも、過去の作品を全て堪能した人でも十分に楽しめる。
『天気の子』は「誰」を描いているのか
『天気の子』は、特定の〝キャラクター〟ではなく、普遍的な〝誰か〟を描こうとしている。言うなれば〝その辺にいそうな今どきの子〟だ。それを象徴するために必要な要素だけで〝キャラクター化〟されている。だから、登場人物そのものについて、どうこう言うことにあまり意味はない。
物語上の主人公は、高校一年生の森嶋帆高と自称十八歳の天野陽菜である。二人は偶然にも東京で出会い、協力関係になる。だが、そこに至るまでの背景は描写されない。その理由は、画面の向こう側にいる「僕と君」を作ろうとしていないからだ。
帆高は島の暮らしに嫌気が差して上京し、東京でネットカフェ難民になりながらバイトを探す。陽菜は弟と二人暮らしでバイトで生計を立てていたがクビになる。ここに設定された状況や、新宿という場所、出会いの偶然性といった細部に、本質的な意味はない。それらのディティールは「実は何でもいい」のである。
それよりも、そんな状況に放り込まれた若者が大量に存在する現代を浮き彫りにした事の方が重要だ。本作の意図は、その状況で行動せざるおえなくなった「彼ら」を追って描くことにある。だから、この作品で語られるストーリーの背後には、類似のエピソードが大量に存在する。似たような状況に置かれている若者が、今も実際に存在しているからだ。
前作『君の名は。』には、瀧と三葉という明確なキャラクターがいた。彼/彼女は、生活の背後が描かれ、行動原理の因果がきっちりと描写されていた。そういった意味で、前作は作品世界の内部に閉じて完結していた。今回はその枠組を大きく超える設定になっている。
本作『天気の子』で描かれているのは、現実世界にいる「誰か」だ。それはアニメーションという表現において、虚構の中――いわゆる「異世界」や「夢物語」――に封じ込めて、〝キャラ〟として愛でる対象ではなく、あなたの周囲に広がる地続きの世界と接続する装置だ。
それは「あなた自身」には成りえないが、「思い当たるフシ」には接触するかもしれない。あなたの知り合い「自体」ではないが、その「面影」を想起させるかもしれない。そこには「天気」という共通問題が横たわっていて、「天気」の問題に向き合っているのは、「虚構の世界にいる僕と君」ではなく、「現実世界に生きる私とあなた」なのだ。
このテーマの大きさは、宮崎駿監督が次に取り組んでいる『君たちはどう生きるか』に通じるものがある。本作は、それぐらい視座が高い。「彼らはそう生きた」「君たちはどう生きるか」だ。
それでは「天気」とは一体何なのだろうか。なぜ陽菜の気持ちで「天気」は変えられるのだろうか。
『天気の子』における「リセット」の重要性
天気の前に、この作品における「リセット」の重要性を語る。
この映画の視聴者層とターゲットは理解した。ならば、本作品を観る際に日常的にアニメを消費するようなコアなファンの視点を導入するのは得策ではない。バイアスを含んだ視点は誤解を招くし、せっかくの作品を楽しめないのは損だ。なるべく頭を「リセット」して、純粋な視座から眺めた方が『天気の子』は楽しめる作品だ。
過去の知識や事前情報は、偏見というフィルターを生む。それを通して本作品を観たならば、作中に違和感や不快を覚える箇所がいっぱい生まれるだろう。そして、その違和感こそが大事なのだ。
新海監督はインタビューの中で『天気の子』に込めた想いを「より批判されるものを作ろう」「もっと叱られる映画にしたい」「『君の名は。』に怒った人をもっと怒らせたい」という言葉で語っていた。
つまり、作中に感じる違和感や不快は意図的に仕組まれたものであり、そう感じるのは「正しい」ことなのだ。重要なのは、その感情と向き合い、ちゃんと考えることである。自分は何に違和感を感じ、何を自然に受け入れたのか。その描写になぜ嫌悪感が生まれ、なぜあのシーンは気持ちよかったのだろうか。それを考えずに、感情をそのまま吐き出す行為を、あなたは「正しい」と思えるだろうか。
ここに強烈なアンチテーゼを感じた。監督は「いわゆるオタク」に対してリセットを要求している、あるいは「オタク的な構造」に対してリセットをかけようとしている、そう考えられるのではないか。
今までアニメ作品を批評するには、過去の文脈を動員してコンテクストで語る形式が強かった。あるいは、ネットで入手した知識をフル活用してマウントを取る手法が強かった。なぜなら業界や作品自体が、そういう構造になっていたからだ。
過去に作られたテンプレが流用され、キャラクターが記号化し、属性によって分類され、内容なき表層だけで量産される作品群は、ビジネスモデルとしては成功した。だが、その結果生まれたのが今の現状だ。
もし監督が「みんなの望むもの」を作ろうとするならば、違和感の生まれる要素や不快に感じるシーンを、できるだけ排除するだろう。アニメを積極的に観る人たちが「こうあって欲しい」と思う要素で画面を満たせばいいからだ。
だが新海監督はそうしなかった。なぜなら、それは彼が作家性を発揮したからであり、それを実行できる境遇にいたからであり、そうすることを決断したからである。
だから、その決断に対して古い価値基準で批判することは、それ自体が自己批判として返ってくることを意味する。つまり「リセットできなかった人」は自動的にあぶり出される仕組みになっているのだ。まるで作品に対する言及がリトマス試験紙であるかのように、批評する者もまた批評されるのである。
この作品が言及している領域は文学に近い。文学は世間や時代を別の視点から[語る/読む]行為である。例えるなら、みんなが当たり前だと思っている物事に、光を差し込む行為である。あるいは、時代と共に透明化してしまった枠組みを、ちょっとずらして見えるようにする行為とも言える。いずれにせよ、一つの主観から別の視点に切り替えれば、物事は違って見えるよ、ということを表現するためにある(アウトプットの形式は問わない)。
何が言いたいのかというと、『天気の子』はそれぐらい「大きなこと」に挑戦している作品だということだ。工業的な手法で量産された作品と一緒の視点で語ると、読み違えるアニメだということだ。それは私も観終わってから気づいた。だから鑑賞している最中に感じた違和感を一つ一つ「リセット」する必要があった。
「アニメ弁慶」であるほど、『天気の子』を観ている最中に気に入らない点や違和感が大量に出てくるだろうが、それを一個一個「リセット」して判断を保留にしてみて欲しい。観終わった後に他の作品と比較して、あるいはコンテクストを並べて批判したい気持ちを、一旦「リセット」してみて欲しい。
そして冷静になって考えてみると、「あれ、この作品……もしかして凄いことやってるんじゃないの」と、じんわり思えてくるかもしれない(保証はできません)。
この作品で描かれている「天気」とは何か
この作品で描かれる「天気」とは、「世の中の雰囲気」や「みんなの気持ち」の象徴である。天気は人の力ではどうにもできない現象だ。にも関わらず、それは広範囲に渡って影響を及ぼし、人の心理や社会にも影響を与える。
政治的な不安や、安定しない経済、不幸なニュースや、ネットに蔓延するネガティブな感情。そういったものが世の中を取り巻き、時代という名の共通認識を作り出す。それを作中では「止まない雨」として表現している。
「それは違うよ」と反感を覚えた人、その感覚は正しい。「みんながそう思っている」という全体の雰囲気に抗う勇気こそ、この作品は要求しているからだ。そんな感情を抱いた人にこそ、自分にとっての「晴れ」を探して欲しいと願う。
陽菜の「晴れ女」の力を使った仕事では、個人的にささやかな希望を叶える依頼が多かった。フリーマーケットの会場を晴れにしたり、流星群が降る日に天体観測をできるようにしたり、競馬で賭けたい馬が雨だと調子が出ないから止めて欲しい、という内容だ。
個人のありふれた願いは、局所的に「晴れ」を作れるのだ。世界情勢が不安でも、景気が回復しなくても、政治が上手くいってなくとも、人の気持ち次第で日常を明るく過ごすことが出来るということだ。
だから、花火大会を晴れにする企画でテレビ中継されてしまった後は、人間の温かみが消され、心ある希望は失われ、帆高と陽菜は「世の中」に飲み込まれそうになる。以降、二人は全ての依頼を断るしかなかった。
最後に残ったのは、夫を亡くした老婦人が初盆を晴れにしたいという気持ちと、娘と遊ぶために公園を晴れにして欲しいという須賀の願いだった。本来、人間一人が対応できる規模なんて、そんな程度のものなのだろう。
陽菜の内面が現実の天候とつながっているのは、それが物語のフィクションとしての装置だからだ。本来、人の気持ちを物理世界に反映させることはできないが、それぐらい強く信じ、願う行為をしたならば、あるいは――というロマンである。しかし、現実世界は無理でも、内面世界の「天気」を変えることは全ての人に備わっている潜在能力だ。それを描き出すためのギミックとして、納得してもらうしかない。
「晴れ女」の仕事を止めた二人の世界に、再び雨が降り続ける。陽菜は「人柱」になるということを半ば受け入れ、「狂った天気」を戻そうとする。しかし、帆高が叫んだのは「陽菜、自分のために願って」だった。
彼は陽菜が人柱として世の中のために犠牲になるよりも、彼女一人が助かり「彼と彼女」の関係性さえあればいいと願ったのだ。
二人は再開し、世界は元に戻り、また新しい日常が始まる――果たして、これは「セカイ系」だろうか?
これは「セカイ系」への回答である
物語のターニングポイントで、陽菜は「世界の終わり」を変えるために「自分が犠牲」になってそれを止める。典型的なシナリオでは、ヒロインは主人公の元へ[戻り/戻らずに]、世界は「正しい状態」になって、エンディングを迎える。そのような定番を、この作品ではあっさり覆す。
帆高は「陽菜、自分のために願って」と叫んだ。
須賀は「世の中なんてどうせ始めっから狂ってる」と言った。
陽菜と再開した帆高は最後に「僕たちは、大丈夫」と言った。
そのセリフは、全て外に向かって発せられている。本作で描かれているのは現実世界の「誰か」だ。そして「天気」は時代を象徴する気分だ。これまでに拾い集めてきた点を線でつないでいくと、全ての要素が外の世界につながっている。
政治的な正しさ、みんなの意見、世間の目――現代人はそのような「天気」に押し流されそうになっている。しかし本当に大事なのは、一人ひとりの内面だ。人間の心の中にある気分だ。
その気分は小さな幸せで変えられるかもしれない。その幸せは、フリーマッケットの一日にあるかもしれないし、天体観測の瞬間に感じるかもしれない。彼岸に思いを馳せる夕暮れや、公園で遊ぶ日常にあるかもしれない。
あの東京で行き場の無かった帆高が、須賀と夏美と築いた一時の疑似家族に幸せを見出せたのかもしれない。陽菜と凪の暮らしに帆高が加わったことで、疑似家族のような瞬間的な幸せがあったのかもしれない。ここで言う「家族」とは、この世界に心をつなぎとめる「僕たちしか知らない秘密」だ。「世界」の「秘密」は「君だけ」と分かち合えればいいのだ。
「僕たちは、大丈夫」
この最後のセリフは、もう、どうしようもなく、新海監督から若い世代へ向けた最大級のエールだ。この宣言は本当に力強いと思う。その真意は、どんなに世の中が暗い情報で溢れていても、自分たちで気分は変えられるということであり、もはや外部の「天気」は関係ないと言うことでもある。
本作品で描かれているものは「セカイ系」などという閉じた世界には断じて収まらない。エンディングの先には、各々が持ち帰り、自分自身で決着しなければいけない「大きな物語」が待っている。その先には次の帆高や陽菜がいるわけだし、どこかで帆高や陽菜に出会うかもしれないからだ。
この終わり方はポジティブでハッピーエンドであろう。例えそれが、降り続ける雨が止まない世界でも、花見はできるという人がいるのだから。
例の広告が描かれる必要性はあったのか
例の広告とは「ヴァ◯ラの求人」であるが、あのシーンは描かれる必要があった。
『天気の子』も過去の新海作品の例に漏れず、背景美術に対する異様なこだわりが際立っている。新海作品の重要な要素として背景美術は欠かせないものだが、本作では今までの作品とは違う描かれ方が成されている。
『秒速5センチメートル』は、主に「情景」として背景が描かれる。画面に映るのは、思い出補正された「あの日の記憶」であり、そこには写実主義的リアリズムを超越した神秘性が含まれている。その意味で『秒速5センチメートル』の背景は印象派的なアプローチで描かれており、そこに「思い当たるフシ」を重ねられた者だけが感情移入できる仕組みになっている。
『言の葉の庭』は、光と影の煌めきを補強した演出になっている。これは主人公・秋月孝雄の一人称視点が強調されているからであって、十五歳の高校一年生の男子の、真剣な眼差しから見たときの風景だ。画面に映る背景には、心の「ざわめき」や「うつろい」がにじみ出ている。その意味では表現主義的なアプローチと言える。
『君の名は。』は理想化された風景だ。物語で語られるスートーリーとは別に、田舎には里山の良さが描かれ、東京には憧れの暮らしが描かれる。宮水神社の御神体が置かれている山奥に行けば見事なランドスケープがあり、黄昏の山頂で二人が再開する場面では奇跡の一瞬が映し出される。これらは言ってしまえば「インスタ映え」する景色であり、別の言い方をすれば「死ぬまでに見たい絶景百選」のような映し方である。表現手法としては「雑誌に掲載するフォトショ補正済み写真」のようであり、良い意味で工業主義を肯定的にとらえたアプローチだと言える。
『天気の子』の背景は、登場人物の心理を徹底的に突き放している。そこに横たわるのは、圧倒的に冷たい現実だ。新宿の街に情念を介入させる余地は一切ない。景色は猥雑で、光は下品で、情緒に触れる機会はここにはないのだ。部屋の中はわざと汚く描かれている。壁は汚れ、床には物やゴミが散乱し、空間は狭く低く息苦しい。窓から見える空は限定されていて開放感はない。そんな無情な暮らしを私たちは望むだろうか。だが、地に足つけて生きるとはそういうことなのだ。見たくもないものが勝手に目に飛び込んでくる。聞きたくもない音がそこら中で流れている。それが「都会」という現象であり、あの個人の尊厳を無視して圧倒的な力をもって土足で踏み込んでくる「何か」が、「例の宣伝トラック」なのである。
人間が作り出した社会に気に入らない部分があるとしたら、それを作り出したのもまた人間であるということを忘れてはならない。『天気の子』に出てきた描写の中で、自分はいったい何に嫌悪し、何に癒やされたのか、もう一度振り返ってみる価値はある。
その「何か」を嬉々としてネットにアップしている自分を想像してみて欲しい。それで本当に自分の心に「晴れ」をもたらすことができるのか、自分の大切な誰かと「世界の秘密」を共有することができるのか、考えてみて欲しい。
これだけの「深度」が新海作品の背景美術にはある。それを単なる「神作画」という一言で終わらせてはいけない。絵は線と色だけでできているわけではないのだ。
代々木会館というロケーションを選んだセンス
物語に登場する重要な建物として代々木会館が登場する。
代々木会館は2019年8月から解体・建て替え作業が始まる。JR代々木駅で電車に乗ったことがある人なら分かると思うが、あの建物は「次に地震がきたら倒壊するんじゃないか」と思えるほど危うい外観をしている。
この時期に、この物件を選び、このタイミングで公開したのは、本当に絶妙なセンスだと思う。解体されてしまえば、映画のロケ地として行くことはできない。つまり聖地巡礼は不可能になる。これはフィクションが現実に深入りし過ぎた反作用かもしれない。
建物が実際に取り壊された後は、「かつてこの場所にこんな建物があったんだよ」という言い伝えだけが残る。するとフィクションに描かれていた「現実」が、急に虚構っぽくなる。これが映画が公開され、上映され続けているあいだに行われているのだ。映画の中で舞台は半壊する。それは現在進行系で、未来に確定しているのである。
伝聞が残れば、やがて伝説になる。いつか代々木会館の屋上に鳥居があったということが、まことしやかに語られる時が来るかもしれない。ネット上にデマが拡散し、職人がCGを捏造すれば、いけるかもしれない。それをやるかどうかは、各々の行動に委ねられているのだけれど。
あの建物を物語の重要な舞台として選択したのは、新海監督のフィールドワークの成果だ。彼は長いあいだ東京首都圏のJR沿線界隈をカメラを持ってロケハンしていたから、代々木会館の特異性や現在価値に気づいたんだろう。それを作品として出せるタイミングは今しかないと思える。
『天気の子』の凄さ
『天気の子』を見終わって、個人的には「凄い」映画だと思った。その「凄さ」の要素については出来るだけ書いたつもりだが、この「凄い」という感覚には別の真意がある。
正直に言うと、上記に記した内容は映画を観ている最中に全然気づけていなかった。映画を鑑賞している最中に覚えた感覚が、全体を通して観終わった後に徐々に変化して上書きされていくとでも言おうか。二時間のうちに映像を目の当たりにしているあいだは、正当な評価ができなかったということでもある。
これは結構、凄いことをやっている。
部分的なパーツが集まって集合として別の意味を持った時に、パーツとして見えていた要素に別の意味が生まれる。これは映像にしろ、文章にしろ、音楽にしろ、クリエイターが意図的に仕込まないとできない現象だ。
『天気の子』で映される映像は、異化効果を伴って自分の中に別の意味を与える。インターネットを使って中高生がビジネスしていることに違和感を覚えないのならば、それは自分が現代と同化していることになるし、「晴れ女」の出張で報酬をもらうシーンで、観ている側の価値基準があぶり出される。
何かを言及しようとすれば、それが反射して自分に返ってくる。何度も言うように、『天気の子』は作品世界の中に閉じこもるような「キャラクターアニメーション」を描いているわけではない。これは「私たちに関係のある物語」であり、「みんな」がこの物語を見た時の「まなざし」を浮かび上がらせる「鏡」なのだ。
本作の「本当の凄さ」は作品の表層に見つかるものではない。この現実世界と地続きでつながっている部分にこそ宿っているのだ。だからこそ、見る人の背景やコンディションによって評価が代わり、賛否が分かれ、人々に「物語られる」――これが最も重要な要素だ――作品になっているのである。
その同時代性が共有している雰囲気を「天気」として表現し、このタイミングで公開することが「凄い」のだ。そして『君の名は。』の次回作として、あの社会現象の次に、これを創ろうとした新海監督の決意が、予想以上に「凄かった」のである。