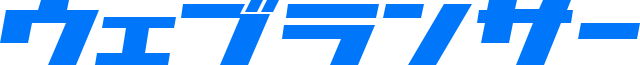ITリテラシーとは何か?
「ITリテラシー」とは、情報技術に関する知識を持ち、それを理解し、活用する能力を表す言葉です。英語圏では「デジタル・リテラシー」と呼ばれることの方が多い分野です。
ITリテラシーが高い人というのは、情報技術に関する知識が豊富で、それをよく理解し、上手く活用できる人ということになります。逆にITリテラシーが低い人というのは、情報技術に関する知識が乏しく、理解に欠け、活用する能力がない人ということになります。
ITリテラシーを高めるには、まず始めに「ITリテラシー」という言葉そのものに含まれる構成要素を把握することが第一です。「IT (Information Technology)」という単語には、非常に多くの分野にまたがる意味が含まれますが、私たちが日常的にリテラシーを問われるものに絞り込むとしたら、コンピューターとインターネットになります。
つまり、一般的な意味で求められる「ITリテラシー」とは、情報そのもの、パソコンやスマートフォンなどのコンピューター、インターネットを扱う能力ということになります。そして、これらの構成要素ひとつひとつも、リテラシーを求められる分野となります。
- 情報リテラシー
- コンピューター・リテラシー
- インターネット・リテラシー
要するに、「ITリテラシー」とは複数の構成要素を組み合わせた総合的な能力ということになります。ITリテラシーを高めようとした場合、どうしてもパソコンのスキルやネットサービスの使い方に焦点を当ててしまいそうになりますが、本質は「情報を上手く扱うこと」の方にあります。本ページでは、ITに関する物事を正しく把握するための基礎教養を解説します。
ITリテラシーを構成する要素
ITリテラシーを高めるには、その構成要素となる「情報」、「コンピューター」、「インターネット」のリテラシーを、それぞれバランスよく取り入れていく必要があります。まずは、各構成要素の基本を把握しておきましょう。
情報リテラシーとは?
情報リテラシーは、情報そのものを自分の目的に合わせて収集し、理解し、活用する能力のことです。情報それ自体は、技術とは関係なく自然や実社会、本や体験の中から得られるものです。つまり、世の中から得られる情報そのものをどのように認識し、いかに扱うかという能力を問われることになります。
コンピューター・リテラシーとは?
コンピューター・リテラシーは、コンピューターを操作して作業を行い、目的を達成する能力のことです。日常生活で使うコンピューターはパソコンやスマートフォンになりますが、これを操作して必要な情報を入手したり、仕事や趣味に必要な成果物を完成させる能力が問われることになります。
インターネット・リテラシーとは?
インターネット・リテラシーは、インターネットの仕組みを理解し、情報の収集と発信を使いこなす能力のことです。インターネットはサーバーやパソコンなどをつなぐ情報網であり、通信によって情報を伝達します。ここでは、情報通信の仕組みを大まかに把握することはもちろんのこと、正しい情報と偽の情報を見分けたり、トラブルに巻き込まれるリスクを回避する能力が問われます。
まずは各リテラシーの現状把握から始める
これらの前提を踏まえた上で、自分に足りない部分を補っていくことが、ITリテラシーを高める第一歩となります。現代では日常生活にITが溶け込んでいるため、意識したり知識を得る前にパソコンやスマートフォンを触り、インターネットに接続していることが当たり前となっています。
本来であれば、ITリテラシーを身につけてからITを活用すべきですが、それは理想論に過ぎません。まずは自分の身の回りのIT環境を把握し、利用する目的を整理し、次に何が必要なのかを考えることが大事です。
情報リテラシーを高める方法
情報リテラシーの基礎は、識字能力と読解力です。こればかりは幼少の頃からの読書習慣、勉強量、教育の質に頼ることになります。情報リテラシーはITリテラシーの土台を固める基盤です。そのため、他の構成要素よりも優先順位が高いリテラシーであると言えます。
情報リテラシーはインターネットが生まれる以前から存在するもので、もともとは学問や研究の分野で提唱された概念です。しかしインターネット以後の世界になっても本質は変わりません。情報には送り手と受け手がいて、それを読み取る行為と、解釈して活用する行為が共通しているからです。
情報リテラシーのゴールは、目的の情報を探し出し、それを正確に評価し、有効に活用できるようになることです。この能力を身につけるためには、インプットとアウトプットが欠かせません。ここでは、情報リテラシーの基礎教養となるポイントを解説します。
感情と理性を切り離して客観的に評価する
情報リテラシーを高めるためには、まず始めに自分の感情と理性を切り分けて考える習慣を身につけることです。ある情報を受け取った時に、自分の感情をいったん切り離すよう意識し、情報そのものが表している客観的な意味、情報の送り手が伝えようとしている意図、情報を受け取った他者が考えそうなことを、それぞれ別の角度から考えてみるのです。その習慣を会得すると、これまで平坦に見えていた情報が立体的になるはずです。
情報を客観的に評価する能力は、日常生活の中で鍛えることができます。テレビやスマホでニュースを見ている最中、小説や漫画を読んで感想を思い浮かべた時、SNSに書かれた内容に触れた瞬間、今まで自分の好き嫌いや直感で反応していた部分を、いったん冷静になって理性で考えるよう意識してください。この方法が情報リテラシーを高めるための基礎となります。
情報を構造的に捉えて分解する
情報を客観的に見る行為と同じくらい重要なのが、情報を構造的に捉えて分解する能力です。情報は時として複雑な物事を簡潔に伝えてきます。しかし、難しい言葉や見慣れない表現に出くわした時、私たちは本当に情報を正しく理解できているのか疑わしくなることがあります。その際に重要となるのが、情報を構成している内容を構造的に捉えて、分解できる箇所を把握する能力です。
たとえば、この記事では「ITリテラシー」を解説するために、三つの構成要素に分解して説明を試みています。言葉というのは面白いもので、目に見えない概念を文字や音声を通じて他者に伝えることができます。逆に言えば、ある概念が表している情報を正しく伝えるためには、その概念を構成している内容を分解して別の言葉で説明しなければならないということです。
私たちは普段の生活で「インターネット」、「スマホ」、「AI」といった言葉を気軽に使っていますが、その仕組みや意味を正しく理解している人はどれくらいいるでしょうか。まずは、こういった日常的に使っている言葉を用いて訓練してみることをお勧めします。
「インターネット」という言葉を構成している要素は何か、「スマホ」を構造として捉えた場合にどれくらいまで分解できるか、「AI」が現代社会にもたらしている影響をいくつ挙げられるか、そのようなことを思考実験として繰り返していくうちに、情報リテラシーは高まっていきます。
情報を参照する能力を上げる
情報リテラシーの優劣は、インターネット・リテラシーの質に直結します。特にSNSやコミュニケーション・ツールを利用する場面では、情報リテラシーが不足していると後悔やトラブルを生む原因となります。それを回避するためには、情報を正しく参照する能力を上げる必要があります。
当然ながら、情報には情報源があります。そして情報源には、「信頼できる情報源」と「信頼できない情報源」があります。「信頼できる情報源」を持つものは「信頼に値する情報」となり得ます。しかし「信頼に値しない情報」は、どこまで辿っても「信頼できない情報源」しか参照できません。それでは、どのようにその二つを見分けるのでしょうか。
信頼できる情報は、客観的な事実が確認できる事象、科学的に証明可能な物事など、第三者が確認した時に意見や結論が一致する情報源を持つものです。天動説が否定されて地動説が信じられるようになったのは、地動説の元になる情報源が信頼できるものだったからです。現代であれば、新商品の発売や犯人の現行犯逮捕といったニュースであれば、それは揺るぎない事実なので信頼に値します。
一方で、信頼できない情報は、客観的な事実が確認できない事象、科学的に証明不可能な物事など、第三者が確認した時に意見や結論が一致しない情報源を持つものです。伝聞や噂話といったものは、どこまでいっても一次情報が不明であり、それを一方的に受け取って信頼してしまうことは危険です。また、デマやフェイクニュースは個人の偏見や悪意が情報源になっていることがあるため、慎重に見極める必要があります。
ちなみに、創作物や体験であれば当事者が発した一次情報が信頼できる情報源となります。誰かが小説や漫画を読んで、あるいは映画やアニメなどを観て書いた感想は、あくまで個人の意見であって、その情報は一方的に信頼すべきものではありません。フィクションにおいて信頼できる情報源は、あくまで作者が発表した一次情報や作品そのものになります。そこから派生した情報をどのように読み取って解釈するかは、あなた自身にかかっています。
情報リテラシーを高めるには、信頼できる情報源を突き止めて参照する能力を上げる必要があります。単なるネット記事や匿名のコメントなどを安易に信用せず、同じテーマを扱った書籍や一次情報を探して、信頼に値する根拠を確かめる術を身につけましょう。要するに「出典」を求めて積極的に参照していこうとする姿勢こそが、情報リテラシーの向上につながるということです。
情報を比較する能力を上げる
情報を参照する能力と同じくらい重要なのが、情報を比較する能力です。情報に付随する情報源は多ければ多いほど信頼性が増します。一つの情報源では完全に信頼できないものだとしても、複数の情報源が揃えば根拠が固まることが多いからです。
情報を比較する能力を上げる際には、大きく分けて二つの方向性で考えます。具体的には、縦につなげて専門性を高めていくやり方と、横に広げて関連性を見つけるやり方です。
情報を縦に比較する場合は、同じテーマやジャンルを扱った本を複数読んだり、授業を受けて少しずつ学んでいくやり方が考えられます。最初は初心者用の情報を参照して簡単な内容から理解し、徐々に中級者用、上級者用へと進んでいく方法です。
情報を横に比較する場合は、別のテーマやジャンルを扱った情報を目的の情報に照らし合わせて、共通点や比喩で考えられる箇所を探します。抽象化やメタ情報と呼ばれる知識を身につけると、専門性では生まれないひらめきを得ることができます。
どちらにしても、一つの情報源で満足せずに、複数の情報を比較して信頼性の精度を上げていくことが、情報リテラシーの向上に必要なことです。
コンピューター・リテラシーを高める方法
コンピューターは、現代の日常生活において欠かせない道具となっています。パソコンやスマートフォンを使って何をするのか、求められる知識や技能は人によって様々です。ここではコンピューター・リテラシーを高める上で必要となる基礎教養を紹介します。
コンピューターとは何かを理解しておく
コンピューターはパソコンやスマートフォンに限らず、日常的に目にするあらゆる機械に組み込まれています。道具としてのコンピュターは様々な形をしているので、その仕組みを理解するには専門的な知識が必要だと思われますが、本質的な部分は共通しています。
コンピューターは、デジタル数字を計算する機械です。計算は入力された数値と、計算式と、出力結果で表されます。それを実現するために必要な機械が組み込まれたものをコンピューターと言います。
コンピューターによって表現される文字・音声・写真・動画といったものは、全てデジタル上の数字で構成されています。逆に言うと、これらを最小単位に分解していくと0と1の数字になります。つまり、コンピューターは入力された情報をデジタル数字に分解して、必要な計算を高速で施し、結果として組み立て直した情報を出力する装置なのです。
まずは、こういった当たり前に使っている言葉を正しく認識することから始めましょう。パソコンやスマホの仕組みがよく分からないという人は、単に基本的な言葉の意味を知らないだけです。AIやクラウドや量子コンピュターといった言葉も、分解して考えれば共通した認識にたどり着きます。ここで敢えて極端な言い方をするならば、コンピューターはただの計算機です。
ハードウェアとソフトウェアの違いを理解しておく
コンピューターの世界には、ハードとソフトの概念があります。ハードウェアはいわゆる物理的な機械のことで、目に見えるパーツで構成されています。それに対して、ソフトウェアはハードを動かすためのプログラムです。
パソコンやスマートフォンは、この二つの集合体であり、様々なハードとソフトの組み合わせで動いています。まずは、この二つが別々の概念であると同時に、両者は互いに組み合わせて使うものだという認識を持ってください。そうでなければ、コンピューターという仕組みを正しく理解するのが難しくなります。
ハードウェアの基本を理解しておく
コンピューターは複雑な計算を行うために膨大なパーツを備えています。それを全て把握しようとすると大変ですが、主要なパーツの名前と役目は覚えておく必要があります。
パソコンやスマートフォンを構成する最も主要なパーツは、計算する頭脳である中央処理装置(CPU)、一時的な情報を記憶しておくメモリ(RAM)、そして長期的にデータを保存しておく記憶装置(HDDやSSD)です。
これらの言葉は、新しい端末を買ったり性能を比較する時に目にするものです。英単語の略称であるため曖昧に覚えている人もいるかもしれませんが、コンピューター・リテラシーを高めるためには、知らない単語の意味を自分で調べて正確に把握する習慣を身につけることが大事です。
パーツの名前や役目を把握しておくと、不具合が生じた際に原因を特定できるようになります。たとえば、パソコンの処理が遅くなった場合に、CPUの性能が足りていないのか、RAMの容量が足りないのか、それとも記憶装置(ストレージとも呼ばれる)の容量が足りないのかを分けて考えることができます。何も知らないと、よく分からないけどなぜか壊れたと言って途方に暮れることとなります。
そして、これらのパーツを乗せて回路でつなぐものを基盤と言います。英語ではメインボード、システムボード、ロジックボードなどとも呼ばれます。パソコンは基盤の上にCPUやメモリやSSDを配置して回路をつなげたものと考えれば、当初よりも理解しやすくなるはずです。
他にも、「Wi-Fi」や「Bluetooth」といった通信機器や、「USB」や「HDMI」などの外部装置を接続する端子などがありますが、細かいパーツは必要に応じて覚えていけば良いでしょう。
ソフトウェアの基本を理解しておく
コンピューターはハードだけでは動きません。当然、それを動かすソフトが必要になります。ソフトウェアの中で最も重要なのが、OS(オペレーティング・システム)です。
OSは、ハードを動かすための根本的な処理やルールを定めるものです。パソコンであれば「Windows」、「macOS」、「Linux」が有名です。スマートフォンであれば「iOS」と「Android」が主流となります。
コンピューターはハードの中にOSというソフトが入っていて、その上で様々なアプリケーションやソフトウェアが動いているものだと認識することが大事です。そして、このように物事を階層化して捉えることが、コンピューター・リテラシーの基礎を固めます。
自分が何を行っているのかを理解する
コンピューター・リテラシーを高める目的は人それぞれですが、真の目標は自分が何をしているのかを理解することです。キーボードのタイピングが早くなるとか、特定のソフトを使いこなせるようになるといったことは、部分的な手段に過ぎません。
まずは、パソコンやスマホを操作している最中に、それがどのように機能し、どんな効果を生み出すのかをイメージできるようになりましょう。ここで役立つのは、やはり基礎教養です。コンピューターの仕組みや情報通信の基礎を知っておかないと、自分が何をやっているのかを自覚する前に、トラブルや事件に巻き込まれることになります。
コンピューターは、情報の入力と出力のあいだで複雑な処理を施す便利な道具です。その「処理」の部分を理解しましょう。コンピューターの動作はプログラムというソースコードで定義されています。それを実行するルールやルーチンのことをアルゴリズムと言ったりします。このようにコンピューターに関わる言葉の意味をひとつひとつ認識していくことによって、自分が何をやっているのかを理解できるようになります。
インターネット・リテラシーを高める方法
インターネットは1960年代から開発が進み、1990年代の後半から一般家庭に普及し始めました。現代では日常生活に溶け込み、なくてはならない存在となっています。そして、多くの人はインターネットの仕組みを理解する以前に、感覚と経験だけで使いこなしています。
インターネット・リテラシーは、情報リテラシーとコンピューター・リテラシーの組み合わせで養います。なぜなら、インターネットの仕組みは情報とコンピューターで成り立っているからです。それを理解した上で、インターネット特有の基礎教養を身につけていくと良いでしょう。
情報通信の基本を理解しておく
インターネット・リテラシーを高めるためには、まず情報通信の基礎を知っておかなければ始まりません。情報通信の仕組みは、人間の対話に例えることができます。対話は、語り手と聞き手の言葉やり取りで成り立ちます。語り手と聞き手は双方の役目が動的に入れ替わったり、参加者そのものが入れ替わったりしながら連続していきます。情報通信もこれと同じです。
わたしたちがインターネットを利用する場合、パソコンやスマホなどの端末を操作して、ブラウザなどの閲覧ソフトを立ち上げ、目的の情報にアクセスします。この時に発生するのがコンピュター同士の対話です。情報へアクセスする許可を求める通信をリクエスト、その通信を受け取った側が返す通信をレスポンスと言います。
このリクエストとレスポンスの連続が情報通信の基本です。インターネットでニュースや動画やSNSを見ているということは、どこかのサーバーにリクエストを送り、レスポンスを返してもらい、そこに保存されている情報を読み込んでいるということです。まずはこれをイメージできるようになることが大事です。
上りと下りの違いを理解しておく
インターネットの通信には、上りと下りがあります。上りはアップロード、下りはダウンロードとも言います。アップロードは、写真をSNSに投稿したりクラウドストレージに資料を保存する際などに利用します。ダウンロードは、一般的なウェブサイトを閲覧したり動画を視聴する際などに行われます。
自分がインターネットを利用している最中に、アップロードやダウンロードが行われているという自覚を持ちましょう。アップロードする際は、全世界に公開されてしまっていい情報なのか、他国の企業のサーバーに保存して問題ないものかを考える必要があります。ダウンロードは、信頼できるドメインの元で行われているのか、自分の端末に保存して大丈夫なデータなのかを考える必要があります。
どちらにせよ、インターネットには上りと下りの通信があり、速度もそれぞれ異なるということを理解しておくことが肝心です。
空間という概念を把握できるようにしておく
インターネットを把握するには、空間という概念が有効です。インターネットに接続していない端末や手元の端末に保存されている領域をローカル空間と呼んだりしますが、これは外部からアクセスできない閉じた空間だからです。
これに対して、インターネットでアクセス可能な空間を何と呼ぶのでしょうか。インターネットは情報通信を行う端末と端末のあいだをとりもつ網です。そのため、インターネットという大きなものが存在しているわけではありません。そこで登場するのが名前空間です。
インターネットは世界中のどこかにあるサーバーやパソコンの場所をIPアドレスという住所で特定します。それを指定する際に、人間が理解しやすい文字列に置き換えたものが、ドメインやURLというものです。
一般的なインターネットは「http (https)」というプロトコル(通信規則)を使います。そして「World Wide Web (www)」という仕組みを使って公開されている情報にアクセスします。そのため、アドレスの先頭が「https://www」となるのです。そして、その後に続く文字列がドメインです。ドメインは企業やサービスを特定する固有名で、固有であるがゆえに情報の重複や混合を防ぎます。
これを分解すると、わたしたちは「https」という規則で「www」という仕組みにアクセスし、ドメイン名の持ち主にリクエストを送っていることになります。つまり、名前によって特定の場所に絞り込んで情報を得ようとしているわけです。
逆に言うと、インターネットに公開されている情報を特定する手段はアドレスという名前しかないため、自分が今どの名前空間を参照しているのか意識するよう心がけることが大事です。画面に表示されている情報が全く同じものだったとしても、名前空間が違えば別物です。トラブルの回避は、こういった基礎知識を得ることから始められます。
利用者側だけでなく開発者側の視点を持つ
インターネット上のサービスは、大企業や特定の団体だけでなく個人が開発したものも多数公開されています。人気のあるサービスやウェブサイトも、実はたった一人で運用しているといったことも珍しくありません。そのため、利用者と開発者のあいだには巨大な参入障壁が立ちはだかっているのではなく、ちょっとした視点の違いがあるだけです。
情報を無料で得られる場合、サービスを無料で利用できる場合、それがなぜ無料で閲覧できるのか開発者側の視点で考えてみましょう。情報の裏側には必ず情報の送り手がいるように、サービスの裏側には必ず開発者の意図があります。
インターネット・リテラシーを高めるためには、サービスを提供する側の意図を読み取る力が必要になります。なぜそれを他者に提供しているのか根源的な動機を想像できなければ、インターネットを安全に安心して利用することは叶いません。
書いてあることが善意なのか悪意なのか、真実なのか嘘なのか、その答えは情報を提供する側の意図の中にあります。動機が明確であれば、判断の担保になります。逆に動機が不明なサービスは慎重に見極める必要があります。
これを読み解くためには、多少のプログラムの知識、ソースコードの読み方、Webサービスの仕組みへの理解などが有効となります。さらに、マーケティング用語やセキュリティの知識なども持ち合わせていると視野が広がります。本格的にプログラマーを目指すほどの勉強を求めているわけではありません。利用者として安全性を確保できる最低ラインを維持すべきだという話です。
開発者になる事は絶対にないと思っている人でも、これらの仕組みを理解する必要性はあります。なぜなら、インターネットは完全に受け身のメディアではないからです。自分で端末を操作し、情報を主体的に閲覧しに行っているのはあなたです。怪しいサイトだったとしても、そこにアクセスして画面をスクロールしたりボタンをタップするのは能動的な行為です。そのため、自分が触れているものの仕組みを理解し、開発者側の意図を読み取り、次の行動を判断する責任は利用者の側にあるのです。
ITリテラシーのとまとめ
これまでの内容を総括すると、ITリテラシーは複数の構成要素からなるリテラシーの集合体であると言えます。そして全てに共通しているのが、基礎教養が大事だということです。まずは各構成要素が表している言葉の意味を理解することから始めましょう。
ここまでは、主に「情報」、「コンピューター」、「インターネット」を主軸に取り上げましたが、他にもメディア・リテラシーやセキュリティとプライバシー、そして法律やモラルに対するリテラシーも求められます。それらは、目的に応じてモジュールを追加していくように覚えていくしかありませんが、基礎教養さえ身につけてしまえば、あとは実践によって経験を積み重ねていくだけです。
最後に、ITリテラシーが高い人の特徴を確認してみましょう。これが全てではないですが、このような特徴を持っている人ほど、ITリテラシーが高い傾向にあります。当然、特定の技術やアプリケーションの操作に秀でていることは大事ですが、それはITリテラシーの上に積み上げていくスキルセットの話です。この中で、現状あなたはいくつ当てはまっているでしょうか。
ITリテラシーが高い人の特徴
- 分からない言葉の意味をすぐに調べる。
- 情報を感情的に受け取らず、理性的に解釈する。
- 物事を曖昧に捉えず、構造的かつ論理的に考える。
- 自分が扱う端末や周辺機器の仕組みを理解するよう努める。
- 反対意見や対立する立場の視点も参考にして次に活かす。
- 物事を相対的に評価し、絶対的な断言は極力控える。
- 幅広い分野に興味を持ち、関連付けて物事を考える。
- 問題が発生したら自己解決できるよう試みる。
- 人に相談する場合は、要点を整理して伝える。
- ITで効率化できる部分を探し、実行する。
- 問題解決のために積極的にITを活用する。
- 新しいものに興味を持ち、取り入れる。
- 情報を受取るだけでなく、発信する。
- 発信する内容は建設的で意義のあるもの。
- 知的好奇心を絶やさない。