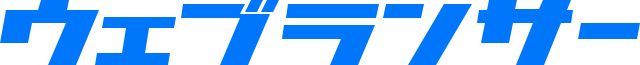あの政権交代を忘れるな『真冬の向日葵 – 新米記者が見つめたメディアと人間の罪』三橋貴明・さかき漣/書評

2009年9月、戦後最大の議席数を獲得し、比例区において日本の選挙史上最多の得票数を記録した民主党の「政権交代」を覚えているだろうか。
本書は、日本中が注目した選挙劇の最中に行われたマスメディアの情報操作を題材にして、報道とは何か、そして情報とは何かを、我々「国民」に突きつける小説。 前途多難な時代の中で、私たちは何を信じ、何を疑えば良いのか? そして、日本を支配するものの正体とはいったい何なのか?
著者はその答えを用意していた。最後まで読めば、それがはっきりと書かれている。そこが本書最大の価値である。
真冬の向日葵 – 新米記者が見つめたメディアと人間の罪
- 著者
- 三橋貴明・さかき漣
- 出版社
- 海竜社
- 初版
- 2012/9/11
2009年9月1日 民主党政権が誕生した日
物語は、歴史上実際に起こった出来事で幕を開ける。舞台は政界。この後、限りなく実名に近い人物や政党が次々に登場し、政治や報道の世界に渦巻く謀略の数々に揉まれながらも、使命を全うしようとする人々の軌跡を見ることになる。
社内に、歓声が響く。
――『真冬の向日葵』書き出し
2009年9月1日。この日、日本国はまさに歴史的瞬間を迎えた。
主人公は就職活動中の大学生、一之宮雪乃。報道の道を志望していた彼女は、新宿へ買い物に出た先で偶然、ある政治家の街頭演説を目撃する。この時の体験が彼女の運命を大きく変えることになった。
雪乃は、ある人物とのメールのやり取りから、自分の知らない物事について興味を持つようになる。そして、就職先のインターンシップを通して、徐々に大人の社会に蔓延る違和感に不信を募らせるようになっていく。
彼女が最初に直面するのは、あからさまに歪曲された報道への疑問だ。本書には、「ネーム・コーリング」や「バンドワゴン効果」という人間の心理に作用する法則が登場する。このような法則の数々は、商売であれ政治であれ〈宣伝〉つまりプロパガンダに使われる。他にどのような法則が存在するのか知りたい方は、水野俊哉の著書『知っているようで知らない 法則のトリセツ』を参照されたい。
そして、このような心理操作に打ち勝つための処方箋として、雪乃は「リテラシー」という言葉を手に入れる。彼女は、ネットの検索を駆使して新たに出会った言葉を知識として身につけていく。
マスメディアの流す情報に影響されて揺れ動く世論。徹底的な印象操作によって国民感情を誘導するメディアは、自分たちの特権的な立場を駆使して政治空間を支配しようとする。情報が多すぎて、あまりにも変化の早い現代社会において、よもや過去の出来事として忘れ去られようとしていた「事実」が次々と活写されていく。政治に直接関係のない言葉狩りや揚げ足取りに終始するメディアの報道に嫌気が差したことを思い出して欲しい。この本には、まさに「あの時」の出来事が書かれているからだ。
マスコミの標的になったのは、第92代内閣総理大臣・朝生一郎と財務大臣・中井昭二である。これらは、小説上の仮名だが即座に特定可能だろう。景気対策最優先を掲げて、日本経済の立て直しを目指す朝生内閣に反発を示す派閥の黒幕が、メディアの力を使って世論操作を演じる。
雪乃は、自ら志した世界の腐敗した一面を見て苦悩する。しかし、この痛みは「真実」を知っているからこそ感じるものだ。著者は、虚構の中に事実を織り交ぜることで、読者に自覚という鏡を打ち立てる。
歪曲報道の手を緩めようとしないマスコミは、更に高度な手法で追い打ちを掛ける。連日報道されるのは、徹底的な人格批判。朝生が金持ちで、高慢で、一般庶民とはかけ離れた感覚を持つ存在であることを刷り込んでいく。そして、メディアは自分たちに都合が良い情報は流すが、「報道しない自由」も行使する。それが、「カード・スタッキング」。張り巡らされた情報によって、偏った印象を形成した民衆は群れを成して動き始める。
人は聖人君子たり得ないのに、他人は他人に幻想を持つ。この人がこれをするはずがない、これをするはずだ、とレッテル貼りをする。そこから外れると、対象を途端に叩く。
――『真冬の向日葵』第二章 洗礼
本書が他書よりも決定的に優れているのはここからだ。物語は、単なるマスコミ批判や、マスコミの情報を鵜呑みにする民衆批判に留まらず、さらに一歩深い部分へと踏み込んでいく。それが、日本を支配するものの正体だ。
この状況を疑問に思い、行動する人間は雪乃だけではなかった、正義感の強い一部の記者は、正しい報道をすべく記事を書く。しかし、その行為はいともたやすく握りつぶされてしまう。雪乃は、財界の重鎮にインタビューする機会を得た際に、自身が抱いている疑問を漏らす。そこでこの人物が語るエピソードが物語のターニングポイントになっている。
この本の中に、山本七平の著書『「空気」の研究』が紹介される場面がある。その部分を以下に引用する。
「いわば彼を支配しているのは、今までの議論の結果出てきた結論ではなく、その『空気』なるものであって、人が空気から逃れられない如く、彼はそれから自由になれない。従って、彼が結論を採用する場合も、それは論理的結果としてではなく、『空気』に適合しているからである。採否は『空気』が決める。従って『空気だ』と言われて拒否された場合、こちらにはもう反論の方法はない。人は、空気を相手に議論するわけにはいかないからである。『空気』これは確かにある状態を示すまことに的確な表現である。人は確かに、無色透明でその存在を意識的に確認できにくい空気に拘束されている。従って、何かわけのわからぬ絶対的拘束は『精神的な空気』であろう。
――『真冬の向日葵』第三章 黒幕の正体
以前から私は、この『空気』という言葉が少々気になった。そして気になり出すと、この言葉は一つの〝絶対の権威〟の如くに至るところに顔を出して、驚くべき力を振るっているのに気づく」
「空気の責任はだれも追求できないし、空気がどのような論理的過程をへてその結論に達したかは、探求の方法がない」
「日本には『抗空気罪』という罪があり、これに反すると最も軽くて『村八分』刑に処せられる」
「統計も資料も分析も、またそれに類する科学的手段や論理的論証も、一切は無駄であって、そういうものをいかに精緻に組みたてておいても、いざというときは、それらが一切消しとんで、すべてが『空気』に決定されることになるかも知れぬ」
制御の効かなくなった歪曲報道の黒幕は誰か? 見えない「敵」を辿って源流近くまでたどり着いたと思った矢先、そこにはただ「空気」があったのである。そんな馬鹿な話があるのだろうか? このようなメカニズムを、別の観点から論じている本がある。1989年、伝承や民族学を通じて「消費者自らの手で物語を作り上げる時代の予兆」を綴った大塚英志が、インターネット登場以降の時代に合わせて過去の著書を新印した『物語消費論改』である。
大塚は『物語消費論改』の序章で、イデオロギーの拡散にはもはや首謀者は必要なく、大衆自らが大衆操作を行う時代が到来したことについて言及している。ここには、世論が「大衆自身による自己動員」によって、主体なき群れと化すまでのプロセスが克明に記述されている。インターネットが一般普及するに従って、例を挙げようと思えばいくらでも出せるような現象が、既に起こっているのだ。
この小説に書かれていることは、多少のフィクションを交えているとはいえ、正にそのような時代背景の中で起こった日本の歴史的事実である。その全てが、冒頭の2009年9月1日に帰結しているのだ。
読者は、この小説を読んで感情的になってはいけない。マスコミを「悪」に仕立て上げて批判すること、マスコミの情報を鵜呑みにして無知なまま流される人々を批判すること、ましてや、当時の自分を批判されたように感じてこの作品を嫌悪すること。それらは全て、過去の愚行を繰り返す行為である。
人を憎まず歴史に学ぶ賢者であれ
将来への不安がまるで消えない時代において、私たちがすべきことは何か。冷静に本書が発するメッセージを読み取って欲しい。多くの犠牲に耐えてきたよう子夫人の言葉が、それを克明に語っている。
歴史には、少なくとも一つの正しい使い方がある。それは「教訓」だ。過去を知った私たちは、未来へ向かって働かせる知恵を得た。あとは、一人ひとりのやり方でやればいい。人を蹴落とすのではなく、自身に与えられた使命を果たす、という方法で。
関連書籍
- 『コレキヨの恋文』の書評
- 『真冬の向日葵』の書評
- 『希臘から来たソフィア』の書評
- 『顔のない独裁者』の書評
真冬の向日葵 – 新米記者が見つめたメディアと人間の罪
- 著者
- 三橋貴明・さかき漣
- 出版社
- 海竜社
- 初版
- 2012/9/11