これは単なるエピソード1に過ぎない『[映]アムリタ』野崎まど/書評
![[映]アムリタ](https://weblan3.com/blog/wp-content/images/entry34_eyecatch.jpg)
この小説を読み始めたら最後、あなたは巨大な世界へ引きずり込まれることになる。いったい何の? 「野崎まどワールド」の、である。
『[映]アムリタ』は、2009年に電撃小説大賞の一部門として新設された「メディアワークス文庫賞」の、最初の受賞作品として選ばれた野崎まどのデビュー作だ。本書はラノベ風の装丁を纏い、ラノベ風の文体で書かれているが故に、「ライトノベルは読まない」と一線を引いてしまっている人が取りこぼしてしまう領域に位置している。
しかし、メディアワークス文庫は一般文芸読者にも受け入れられるようなエンターテインメント作品の創出を目的に作られたレーベルだ。筒井康隆も『涼宮ハルヒの消失』に刺激を受けてメタ的ライトノベルを書いてしまうくらいだから、SFファンならずとも押さえておいて損のない一冊となっている。
[映]アムリタ
- 著者
- 野崎まど
- 出版社
- メディアワークス文庫
- 初版
- 2009/12/16
この作品は、大学生が自主映画を作る物語。なのだが……
物語は、大学に通いながら役者を目指している主人公の二見遭一(ふたみ そういち)が、自主制作映画の撮影に役者として参加しないかと誘われるところから始まる。語り手は主人公で視点は一人称。書き出しは次のように始まる。
大学の巨大な並木を抜けて、掲示板の前で足を止めた。
――『[映]アムリタ』書き出し
休講は無い。学長選挙がどうとか興味の無い話題ばかりだ。一つだけ、学生の訃報が貼り出されていた。原付の事故だそうだ。他人事ながら少しだけ気持ちが重くなる。
まさかこの時点で大きな伏線が張られているとは夢にも思わないのだが、この伏線が主人公にとって全ての始まりであったことが後に明らかとなる。主人公は、知り合いのツテで声を掛けてきた画素はこび(かくす はこび)から、今回撮影する映画の監督は謎の天才少女・最原最早(さいはら もはや)であることを告げられる。そして、アルバイトを終えて部屋へ戻り、最原が作ったという絵コンテを確認しようとした時に、異変が起こる。
この作品の魅力は何かと一言で答えるならば、最原最早の存在に他ならない。彼女は、主人公と会う前から全てを始めていた。読者からすれば、物語のヒロインが登場する前に「全ては始まっていた」ということになる。
何がどう始まっているのかは、本編を読んでのお楽しみ。そして「全て」とは一体何を指すのかを「考察」することができるのが、読了した者だけに与えられるご褒美である。本書は、謎を追って物語を読み進めるうちに先が気になって止められなくなるばかりでなく、次の展開を予想していると、まんまと裏切られる展開になっている。
この作品は、ミステリーとサスペンスの要素を併せ持ったエンターテインメント作品ではあるのだが、読後感はすっきりしない。いや、むしろ得体の知れない薄ら寒さすら漂う。それは何故かと言えば、読者の中に未解決な疑問を残したまま物語が終わってしまうからである。
謎は残されたまま、本書は終わる
私は最原最早の存在がこの小説の魅力だと言ったが、読後に残るのはその天才性よりも、むしろ彼女の「得体の知れなさ」の方かもしれない。なぜそのように感じるのかと言うと、主人公を通して見てきた物語が、「天才だから凄いことができる」という思い込みの誘導とは裏腹に、「実は何もやっていないのかもしれない」という真逆の発想にまで拡張可能な「考察の余地」を残しているからだ。
自分は〈天才〉というバイアスによって何か大きな物事を見落としているのではないだろうか。更に言えば、野崎まどが仕組んだ壮大なレトリックに嵌められているのではないだろうか。そんな不安にも似た疑念が抜け切らないまま物語は終わる。そして、そのような読者の邪推を予測していたかのごとく、著者はあとがきで何も語らないのである。
この時点で、著者がどこまで後の展開を作り上げていたのかは分からないが、少なくとも本書のみをもってこの「得体の知れなさ」を解明することはできない。なぜなら、この作品のエピローグは、「天才」が仕組んだ「脚本」のほんの序章であって、単なる「エピソード 1」に過ぎなかったことが後に分かるからだ。
これからどのような展開が待ち受けるのか気になる方は、以下に挙げた『2』まで一気に読み進めて欲しい。その入り口となる本書が、「野崎まどワールド」の始まりなのだから。
- [映]アムリタ (2009年12月)
- 舞面真面とお面の女 (2010年4月)
- 死なない生徒殺人事件 ~識別組子とさまよえる不死~ (2010年10月)
- 小説家の作り方 (2011年3月)
- パーフェクトフレンド (2011年8月)
- 2 (2012年8月)
[映]アムリタ
- 著者
- 野崎まど
- 出版社
- メディアワークス文庫
- 初版
- 2009/12/16
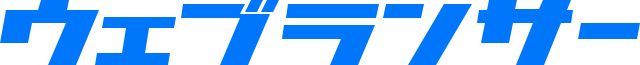
![[映]アムリタ](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51S4r1Z%2B0cL.jpg)